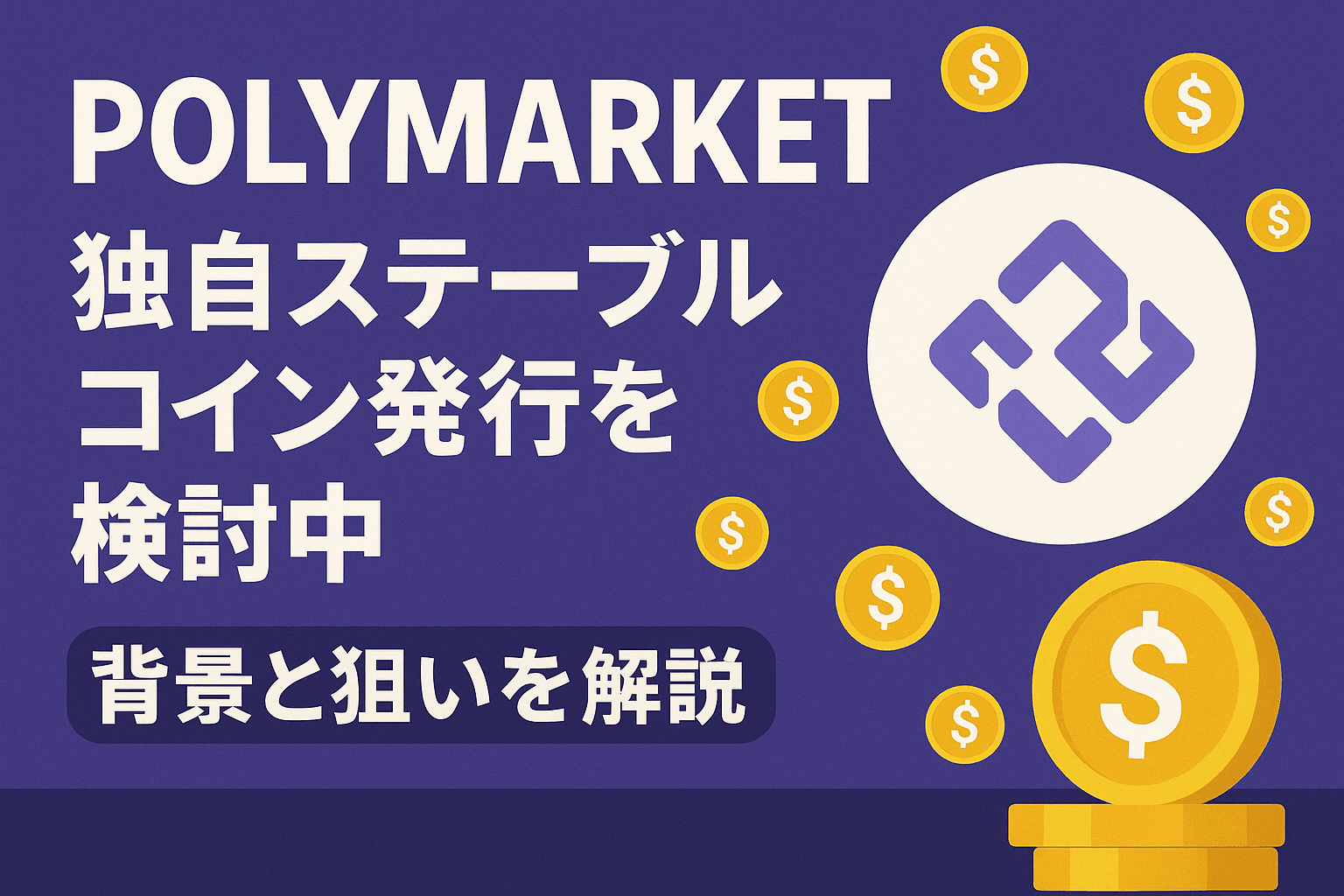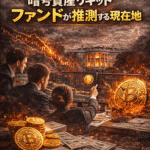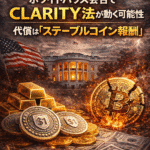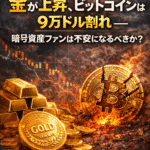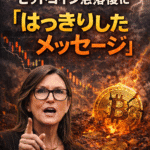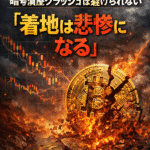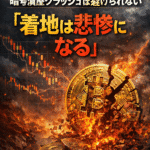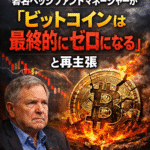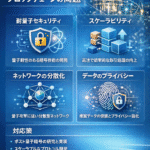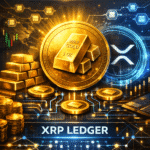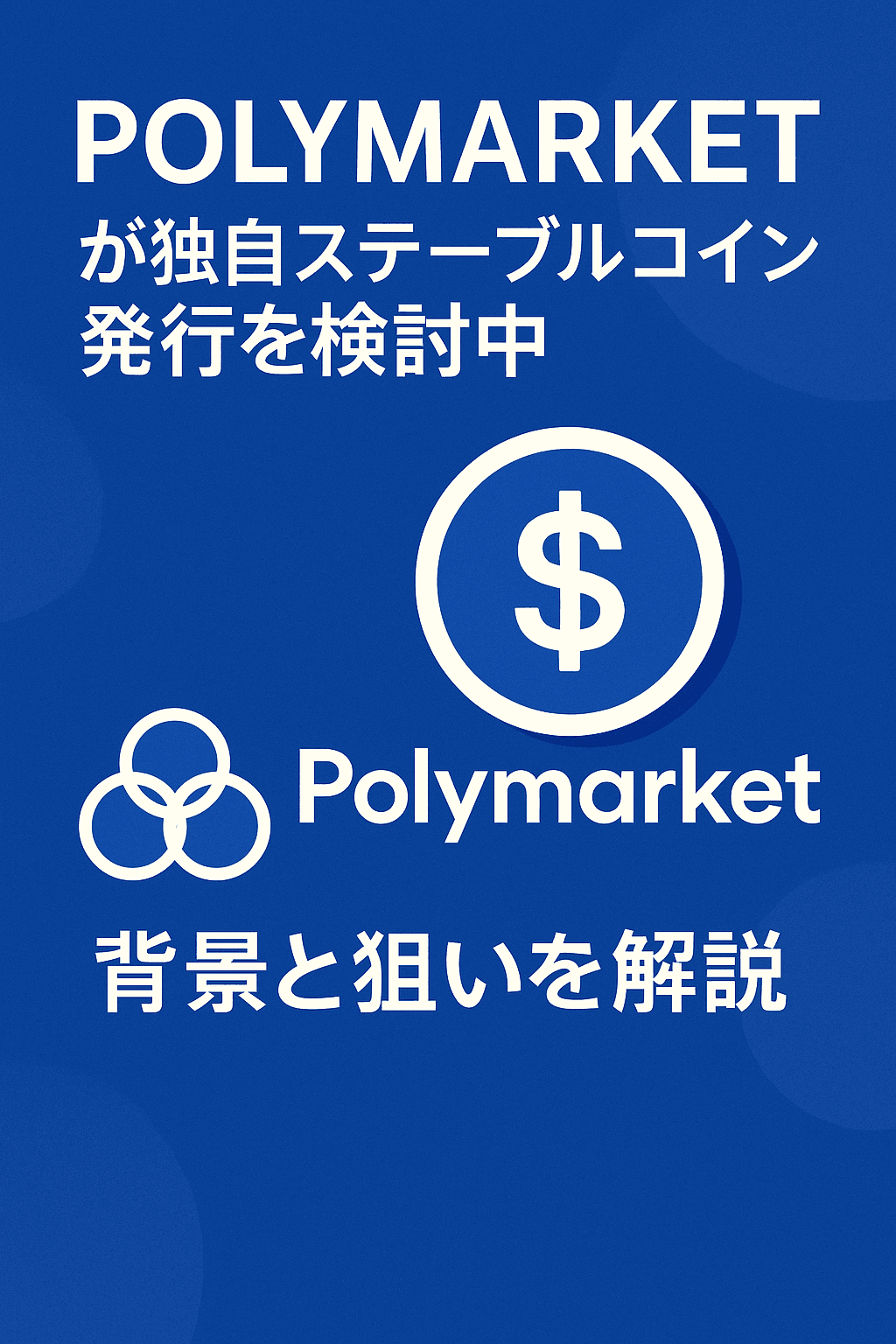
Polymarketが独自ステーブルコイン発行を検討中 ― 背景と狙いを解説
概要
暗号資産予測市場の大手「Polymarket」は、プラットフォーム内で自社開発のステーブルコイン発行を検討していると報じられました。これまで利用者の決済には主にCircle社のUSDC(米ドル連動型トークン)が使われてきましたが、「USDC」に依存せず、自社で発行することで運用リザーブの利回り獲得などを目指す狙いがあります。
背景
- Polymarketの現状
- 近年バリュエーション10億ドルを超え、人気の予測市場プラットフォームに成長。
- 2024年米国大統領選などのイベントだけでも80億ドル近いベットが行われ、月間アクセスは1,590万件超。
- 現状はUSDC等で利用者がベッティングしている。
- 検討理由:自前ステーブルコイン発行のメリット
- Circle(USDC発行元)への収益依存を避け、自社で準備金(米ドル資産等)を運用し、利回り収入(イールド)を直接得る狙い。
- プラットフォームの閉じたエコシステム内での流通に限れば、法規制や複雑なオン・オフランプ提供の負担も何段階か軽減される。
- Circle側とは「USDC預かり残高に比例した収益分配(レベニューシェア)」方式も引き続き検討中。
- 規制環境の追い風
- 2025年に米連邦でステーブルコイン規制を定めた「GENIUS法」が成立し、新規ステーブルコイン業者参入が現実的な選択肢となった。
- 近年はTetherやCircleなど独立系発行体がマーケットの主役だが、プラットフォーム独自コイン発行が参入障壁を下げている。
市場と競争環境
- CircleやTetherは他の取引所や決済企業に対してもレベニューシェア契約を強化中
- 独自コインが続々登場するなか、既存大手は利便性やユーザー体験、収益分配モデルの柔軟化で差別化を図っている。
- Polymarketが独自コイン発行に踏み切る場合、主にUSDC/USDTからの“両替”のみで完結する想定
- 外部ウォレットや従来金融との徹底的な接続・換金(オン/オフランプ)は最低限に抑えられるため、セキュリティや管理のハードルも低い。
- 今後の導入可否や詳細仕様は、引き続き社内で検討中。
今後の展望
- 取引量に対する運用リザーブの利回りが、自社活動・顧客還元に直結するモデル転換の一例となる可能性。
- Polymarketは米国再上陸を目指し、QCEX(米国拠点の企業)買収や法的リスクの解消も進行中。
まとめ
Polymarketの独自ステーブルコイン構想は、予測市場サイトが「収益源多角化」と「ガバナンス強化」を模索する象徴例。米国での新法成立や、従来型ステーブルコイン発行体との収益分配/競争激化など、暗号資産エコシステムの変革期を映し出しています。