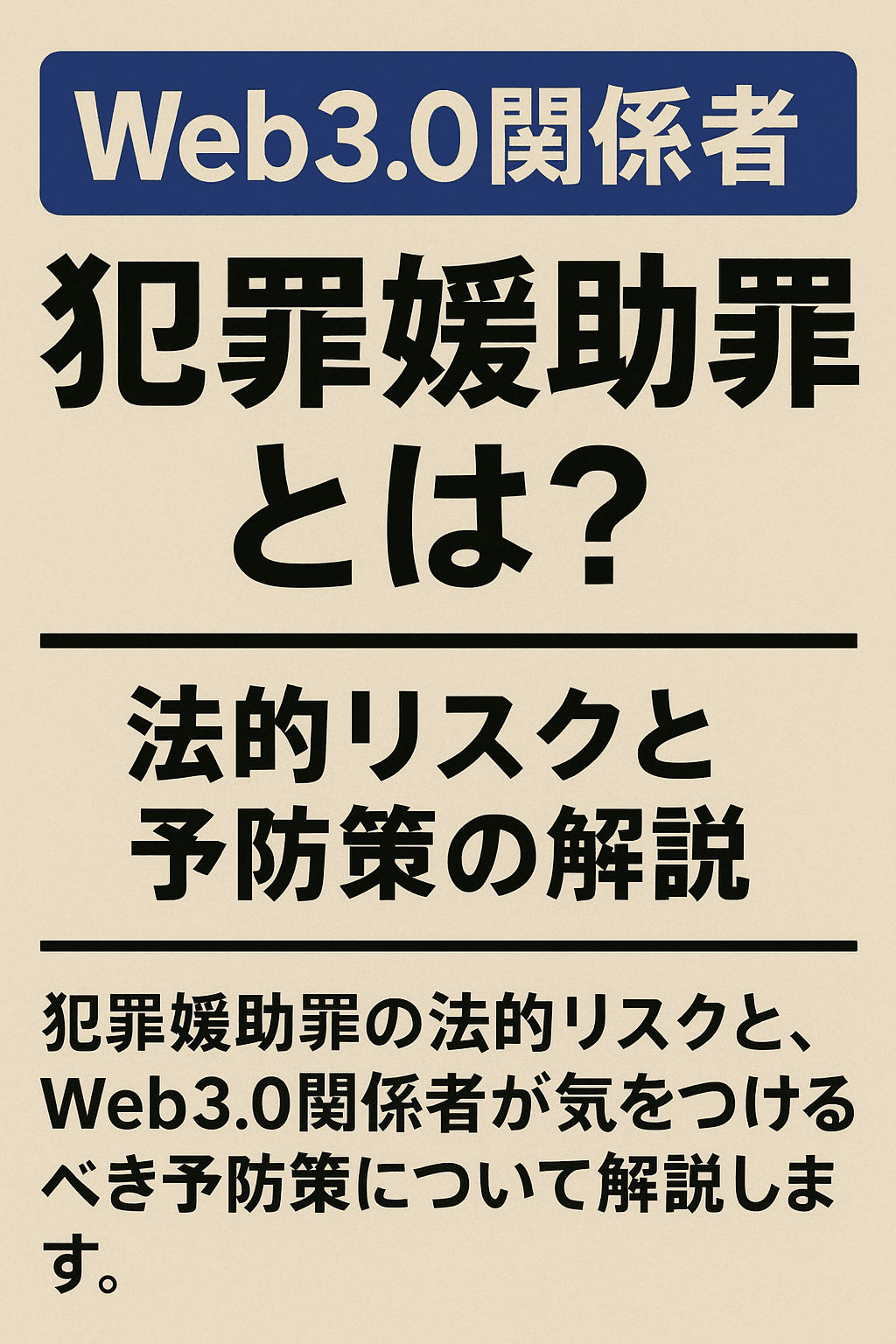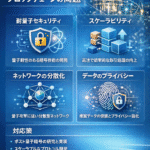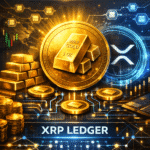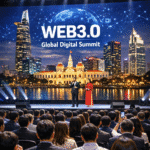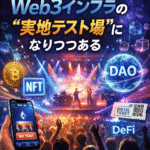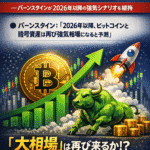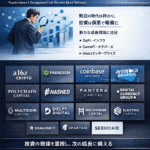Web3.0や仮想通貨の技術革新が進む中で、新たな経済圏やビジネスチャンスが生まれています。しかしその裏で、プロジェクト運営者や開発者が意図せずして法的リスクに巻き込まれるケースも増えています。特に近年、中国をはじめとする一部の国では、「犯罪幇助罪」という形で仮想通貨取引や技術提供に対して厳しい摘発が行われています。
本記事では、仮想通貨を取り巻く実際の事例をもとに、Web3.0実務者やプロジェクト関係者が知っておくべき法的リスクの具体像と、未然に防ぐための対策をわかりやすく解説します。今後の活動において「知らなかったでは済まされない」時代に、どのようにして自分とプロジェクトを守るのか――そのヒントをお届けします。
Web3.0関係者が気をつけるべき「犯罪幇助罪」とは?法的リスクと予防策の解説
仮想通貨やWeb3.0プロジェクトが急速に普及する一方で、法的リスクも同様に高まっています。特に、「犯罪幇助罪(情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪)」として、知らず知らずのうちに犯罪に巻き込まれてしまう事例が増えています。本記事では、Web3.0実務者やプロジェクト関係者が法的トラブルを回避するために知っておくべきポイントを、実際の判例をもとに解説します。
判例から学ぶリスクの実態
ケース1:USDT取引で得た利益が「犯罪資金の移転」と認定
仮想通貨の売買を通じて利益を得ていた複数の関係者が、資金源がオンラインギャンブルや詐欺であったことを「知っていた」と推定され、犯罪幇助罪で有罪となりました。
ケース2:システム開発者が詐欺プラットフォームに加担したと判断
依頼を受けてプラットフォームのリチャージ機能などを開発した開発者が、依頼主の不正行為を認識していたとされ、幇助罪に問われました。
これらの事例では、主観的に「犯罪の意図がなかった」としても、相手側が犯罪を行っていた場合、「知っていた」「知るべきだった」とみなされることで罪に問われる危険性があります。
「犯罪幇助罪」の構成要件とは?
中国刑法第287条の2に基づく幇助罪は、以下の3要件が揃った場合に成立します:
- 犯罪行為に対する実質的な「支援行為」があること
- 相手の犯罪を「知っていた」または「知るべきだった」こと
- 状況が「重大」であること(取引額、件数、利益などが基準を超える)
「知っていた」とされる基準には、規制当局から警告を受けた後も行為を継続していた場合や、取引価格や手法が異常な場合などが挙げられます。
実務者・プロジェクト運営者が取るべきリスク回避策
実務者向け
- KYC(本人確認)と資金源の確認を徹底する
- 怪しい取引相手を見極め、必要に応じて取引を拒否する
- 異常な取引頻度や価格に注意し、不自然なスキームには関与しない
プロジェクト運営側向け
- 利用規約に「不正使用禁止」や「責任は利用者に帰属する」旨を明記
- APIの使用権限を段階的に管理し、異常な利用は遮断
- 大口の資金移動などに対しては監視体制を強化する
まとめ:主観的に無実でも、法的責任を問われる時代
仮想通貨やWeb3.0領域においては、形式的には合法な行為でも、その背後に違法行為があれば、幇助罪として処罰対象となる可能性があります。KYCやAML対策の強化、ユーザー行動の監視、契約文書での免責明記など、実務的かつ具体的な対応が求められます。
問題が発生した場合や不安がある場合は、速やかに専門弁護士へ相談することが重要です。Web3.0の発展には、法令順守とコンプライアンスが不可欠です。